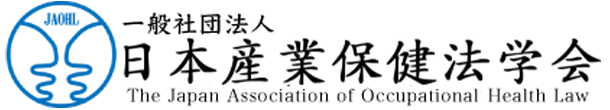人事労務座談会「障害者雇用と障害者雇用が企業にもたらす変化」
《インタビュー》
1.登壇者紹介
森本:
本日は松山先生にお話を伺います。まずは自己紹介からお願いします。
松山:
社会保険労務士です。福祉施設職員として10年以上勤務後、2006年に開業。2017年に法人化。現在は①通常の社労士業務、②障害年金手続き、③障害者雇用支援の3本柱で活動しています。
小島:
人事労務支援を主に行っている弁護士です。本日は、障害当事者や障害者雇用する企業を支援するだけでなく、障害者を自ら雇用することに挑戦しておられる松山先生のお話をうかがえるのが楽しみです。
彌冨:
産業医です。30年にわたり製造業で障害者支援に携わってきました。企業内外の多様な支援機関と連携し、現在は障害者職業センターの医療支援者としても活動しています。
江黒:
社労士・公認心理師です。障害者雇用支援を行いつつ、学習障害(LD)への理解を深めるため学会にも参加しています。
森本:
産業医を本業にしつつ、社労士・公認心理師などの資格も持っています。本日は司会も務めさせてもらいます。
2.採用の進め方
森本:
このたび参加している他の先生方から松山先生に伺いたいことを事前にお寄せいただいたのですが、大きく「採用」「定着」「キャリアアップ」「制度」に分けられます。まずは障害者の採用について、どう進めればよいか、松山先生に伺いたいのですが。
松山:
採用を進めるにあたり、多くの企業はまずハローワークに相談や登録に行きます。ハローワークには障害者雇用に関する専門の窓口が設置されていて、障害者雇用に関する専門知識を持つ相談員がいます。また、ハローワーク経由で採用した場合、助成金やトライアル雇用の制度を活用できますし、法律面のアドバイスも受けられる点がメリットです。ただし本人や企業の状況を深く理解したマッチングまでは難しい面もあります。それ以外の機関としては「なかぽつ(障害者就業・生活支援センター)」や「就労移行支援事業所」です。これらは企業や本人を長期間支援してくれるため、深く理解してくれます。私は顧問先にはまず就労移行支援事業所を勧めています。理由は、採用前に実習を受け入れることで「自社に障害者を受け入れる準備があるか」を確認できることや、採用後に定着支援があることです。
森本:
なるほど。なかぽつの役割はどうでしょうか。
松山:
なかぽつは生活面と就労面を一体的に支援し、中立的な立場で見てくれます。なかぽつは企業と本人双方にとって安心できる調整役になります。採用・定着のためには、ハローワーク、就労移行、なかぽつなどの特性を理解し、組み合わせて活用するのが望ましいです。
3.採用の準備
森本:
企業から「障害者を雇用しないといけないが、準備が整っていない」という声をよく聞きます。では、何をもって準備ができている・できていないと言えるのでしょうか。
松山:
一般論ではなく、私たちの事務所の経験からお話しします。 まず「研修」や「見学」だけでは不十分でした。成功事例に感動しても実感が伴わないからです。そこで私たちの事務所では実際に就労移行支援事業所から実習生を受け入れることを始めました。 弊社は小さな組織なので「やる」と決めて強引に始めました。重要だったのはマイナス意見を聞かずにやってみること。ただし、単に受け入れるだけでは現場が疲弊するので、経営者が中心になって支えました。 実際に実習を受け入れる中で、弊社の「準備不足」が明らかになりました。
例えば、障害年金チームは日頃から当事者対応をしているため、柔軟に調整できたのですが、一方で、企業チームは知識やマニュアルに頼りすぎ、予定表を過度に細かく作ってしまい、それが逆に当事者の混乱を招き、パニックになることがありました。この経験から、障害者雇用の準備とは、マニュアルを整えるというようなことは後でもよくて、私たちの側に問題があってエラーが起きることを前提とし、それでもなんとかなるんだと受け止める体感を持つことだと考えています。
4.定着のために必要なこと
■勝手に意味づけずに直接聞いてみる
森本:
たしかに実際に雇用した後にトラブルが起こることがありますよね。小さなトラブルだと修復が可能でしょうが、大きなトラブルで関係性が切れないようにするにはどうすればよいでしょうか。
松山:
ポイントは2つあります。
- 採用までの人生を受けとめる
多くの企業は「入社したその日からその人を知っていく」スタンスで臨みますが、発達障害や精神障害のある方は、過去に繰り返し怒られてきたために、トラウマを抱えていて、自己肯定感が低いことが多い。そのため、当人が自分の言葉で伝えるまでに時間がかかるかもしれないと理解しておくことが重要になります。 - 心を相手の視点に置く
その中で、当事者の言葉に私たちが勝手に意味を付けてしまうことで、当事者が傷つくことが多い。エラーが起きたら、「なぜそうなったのか」を相手の視点に心を置いて考えることが大切です。
実際にこんなことがありました。
障害のあるスタッフが初チャレンジのセミナー登壇後に2日欠勤しました。周囲は「(人前で話をした)ストレスで休んだ」と推測しましたが、本人に実際に話を聞いてみました。そうすると、当日、周りが「(セミナーの登壇で疲れただろうから)懇親会に来なくてもいいよ」と配慮しすぎてしまったことが原因でした。本人は悲しい気持ちになってしまったのです。
――つまり「想像で配慮する」のではなく、本人に直接聞くことが定着支援の本質だと学びました。
■土台としての日常生活の重要性
彌冨:
障害者のなかには、家族の支援が少なかったり、独り暮らしで生活のサポートが必要な方もいて、就業支援だけでは生活面が見えず、支援が分断されることも少なくありません。生活が安定していないと就労の継続も難しいと思いますが、この点についてどのようにお考えですか。
松山:
日常生活こそ就労の土台です。
実際、ゴミ屋敷状態で睡眠や食事が不十分なまま働こうとしても、集中力や体力が保てません。だからこそ、なかぽつ(障害者就業・生活支援センター)、市区町村の就労支援センター、訪問看護、ヘルパーなど、家の中に入れる支援機関と連携することが必要だと思います。
■強みを広げるキャリア形成の意識
江黒:
多くの企業は「この穴を埋めるために雇う」という形で採用します。しかし同じ仕事を続けると、長期的には本人が嫌になって辞めてしまうこともあります。能力を伸ばしキャリアにつなげるにはどうすればよいでしょうか。
松山:
障害の有無に関わらず、同じ業務だけを延々とやるのは誰にとっても苦痛です。大切なのは「その人の強みをどう広げられるか」を考えること。単なる穴埋めではなく、成長や変化の可能性を見込んだ業務設計を企業側が意識する必要があります。
■本当の心理的安全性
松山:
障害のある方は、過去に「怒られる」「解雇される」といった経験を繰り返してきた方が多いです。やる気はあってもやり方が分からず、ワーキングメモリの特性などからうまく仕事に必要な内容が定着できずに注意されてしまう。そのため、もし「やりたい」と言って失敗してしまったらいけないと考えてしまい、「やりたい」ことが言えなくなることもあります。
「この場では言っても大丈夫」と思える心理的安全性を会社がつくることがまずは大切なことになります。私の事務所では40人以上の実習を受け入れてきましたが、心理的安全性があると発達特性が目立たなくなることを実感しています。
採用からのステージは大きく3つに分けられます。
- 採用前・直後:ミスをしても「嫌いにならない」と伝え続け、孤独や解雇への恐怖を和らげます。
- 数カ月後:孤独にならないと分かって初めて「これをやってみたい」という気持ちが出てきます。
- さらに数カ月後:「未来に自分がいる」と実感し、会議や交流の場に参加してアイデアを出すようになります。
つまり、「職場に心理的安全性があると感じてもらう」 → 「やってみたいと当事者が感じる」 → 「職場の未来に自分がいると当事者が実感する」 という流れがキャリア形成につながるのです。
江黒:
心理的安全性には二面性があると感じています。
何でも言える関係は一見安全そうに見えますが、「権利がある人しか言えない」状態になることもあります。その場合、効率は上がっても障害者雇用は失敗につながります。やはり「未来に自分がいる」と思える経験を積ませることが大切で、その場では無駄に見える場面でも会議や打ち合わせに参加させることが成長につながると感じました。
松山:
心理的安全性は「何でもOK」ということではありません。
「甘やかす」のではなく、社会人として必要な行動を教えることを大切にしたいです。心理的安全性は「一人の人として向き合うこと」と両立できることを大事にしていきたいです。
彌冨:
私の職場でも、元管理職の在籍型ジョブコーチが、合理的配慮と並行して「社会人として守るべきこと」を粘り強く指導しており、その効果を実感しています。心理的安全性を確保すると同時に、社会人としての基準を根気強く伝える姿勢の重要性を改めて感じました。
5.働きやすくなる制度と合理的配慮
森本:
ここまで実態や気持ちの部分を伺えたので、次は制度面についてお聞きしたいです。例えば「この制度を入れたらうまくいった」といった事例や、他にはあまりない工夫などがあればぜひ教えていただけますか。
松山:
テレワークは分かりやすい例ですね。ただし、障害の種類によって向き・不向きがあります。ASDや聴覚過敏のある方は在宅の方が適していることもありますが、ずっと在宅でよいかというとそうではなく、月1回の面談やマニュアル整備と組み合わせることが大切です。
また、ある介護施設では全員がインカムを付けていて、障害の有無にかかわらず「分からない時にすぐ聞ける」環境を作っています。チャットの常時利用も同様です。耳からの情報は合わない人もいますが、話し方をゆっくりにするなど工夫すれば効果的です。
森本:
なるほど。では、時短勤務についてはいかがですか。
松山:
時短勤務は有効ですが、本人も企業も「どのくらいが最適か」は試してみないと分かりません。6時間や6.5時間など、電車の混雑も含めて調整してみるとよいです。ただし時短勤務では必要な生活費を稼ぐことが難しい場合もあり、独居か家族同居か、家族の支援があるかなどを確認し、必要に応じて障害年金を組み合わせることもあります。
合理的配慮という点では、「人×業務」だけでなく「人×人×業務」と考えることが大切です。例えば経理をやりたいけれどメモが取れない人には、メモが得意なスタッフを同席させる。すると双方が役割を持ち、双方の成長にもつながります。
森本:
なるほど。合理的配慮の線引きはどこまでなのか、よく質問されます。その点について先生の考えを伺えますか。
松山:
私は「それをすることで本人が働きやすくなり、活躍できるようになること」が合理的配慮だと考えています。企業は時に本人の行動を「わがまま」と捉えがちですが、それは過去に怒られ続けてきた経験から自己防衛的に出ている言動であることも多いです。特性と人格を混同しないことが大切です。
例えば、障害のあるスタッフが「経理以外の業務は会議室でやらせてほしい」と言ったことがありました。単なる要求に見えましたが、実は「経理以外の仕事は遊んでいると思われるので、他の人のいないところで仕事をしたい」という認知がありました。このように本質を丁寧に聞き取ることが配慮の核心です。
小島:
松山先生が開催している勉強会やよく使われる「感じ合える組織」という表現についても教えていただけますか。
松山:
弊社では「既知から未知へ」という勉強会を開いています。知っていることから一歩外に出て、知らない世界を知る。知ることが愛につながると思っています。企業は就労が主でありながら、病気や生活面まで抱え込んで疲弊しがちです。ところが、異なる立場の人が知識や経験を持ち寄ることで、壁は壁でなくなる。これが「感じ合える」につながります。
つまり、一方通行ではなく、相手の感じ方を聞き、心を相手の側に置いてみる。そうすることで「なるほど、そういうことだったのか」と理解が深まり、別の人への配慮にも応用できます。これが対話であり、合理的配慮の本質だと思います。
6.松山先生が大切にしていること
江黒:
ニーズがあるのだから、社労士の先生がもっと障害者雇用に関わってくればいいのにと思います。
松山:
そう思います。ただ、「ニーズがある」をお金や数字だけで見てしまうと、心が入らなくなってしまう怖さがあるんです。だから、うちの事務所では売上の話をしません。ノルマも課さず、「みんなで一緒にやる」という姿勢を大切にしています。
スタッフにも「法律で人の心は動かない」と伝えています。法律は大事ですが、顧問先に話すときは法律だけの視点ではなく、心に届く言葉で伝えるようにしています。経営者に関心を持ってもらえるように心で伝えています。
江黒:
私は売上を意識せずに動いていたら自然と結果がついてきたタイプなので、逆に悩んでいる先生を見て「行動すればいいのに」と思ってしまいます。ただ、人を動かすには「お金」ではなく「心の切り口」が一番大事なんですよね。
松山:
そうですね。他の先生と組んで学び合うことで、「自分のやり方は違ったかもしれない」と気付けることもあります。就労移行支援でも、障害者手帳を持たない利用者が「今は障害者手帳の取得は嫌」と言っても、仲間の姿を見て「やっぱり取った方がいいかも」と変わることがあります。人は時間をかけて変わる。その変化を待つことが大事だと思います。
彌冨:
今のお話は、健康経営で重視されるVOI(Value on Investment)にも通じますね。VOIは金額に換算しにくいものの、人材の定着や信頼関係の構築といった企業にとって大きな価値を生み出します。企業文化や風土をどう改善するかという視点が重要だと感じました。
松山:
ありがとうございます。障害者雇用の本質は「企業文化をつくる」ことだと思います。障害を見るのではなく「その人」を見る。合理的配慮とは「ここは支援するけど、ここは成長のために頑張ってもらう」と伝えること。人に投資することなんです。
そのためには心理的安全性を整えることが不可欠です。安心できる環境があって初めて、「もっとこうしてほしい」と声を出せます。課題は当事者個人ではなく、組織と個の両方にあります。障害者雇用を通じて「課題は企業側にもある」と気付けたとき、組織は良い方向に進んでいきます。
外部の支援や他者の視点を取り入れて「そうか、相手はこう考えていたのか」と理解し合う。これが「感じ合う」ことであり、企業を強くする道だと思います。顧問先にも「どちらの道に進みたいのか」を問いかけながら支援しています。
森本:
本日は長時間、本当にありがとうございました。