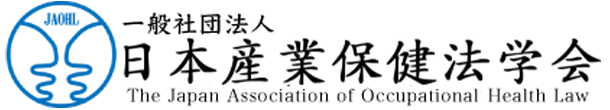人事労務座談会「見過ごされてきた課題:ハラスメント行為者支援の現場から」
| 日時 | 2025年1月27日(火)13時~15時 |
|---|---|
| ゲストスピーカー | 和田隆(メンタルプラス株式会社 代表取締役) |
| 司会 | 熊井弘子(熊井HRサポート社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士) |
| メンバー | 小島健一(鳥飼総合弁護士事務所 弁護士) 森本英樹(森本産業医事務所 産業医・社会保険労務士・公認心理師) 彌冨美奈子(株式会社SUMCO 全社産業医) 岡田睦美(日本産業保健師会会長 保健師・公認心理師) |
現在、職場におけるハラスメント対策の実施は、すべての企業(事業主)にとって義務になっています。そのため、企業はさまざまなハラスメント防止の取組を行っていますが、労働者などからのハラスメントに関する相談は後を絶たない状況です。本座談会では『最新パワハラ対策完全ガイド』などのご著者でもあり、メンタルプラス株式会社代表取締役の和田隆先生をゲストにお招きし、職場のハラスメント、特に行為者への支援に焦点を当てて、意見交換を行いました。
《目次》
■和田先生のご紹介
■ハラスメント行為者とされた管理職の心理
■全力で働いた結果がハラスメント?-管理職の葛藤と健康問題>
■行為者支援が職場を変える
■トップのパワハラ、誰が止める?
■パワーを使わない管理職
■ハラスメント行為者と向き合う難しさ-担当者への支援策
■[総括]行為者支援の再考-カスハラ問題が示すもの
《インタビュー》
<和田先生のご紹介>
熊井
本日はメンタルプラス株式会社代表取締役の和田隆先生をお迎えいたしまして、職場のハラスメントの中で行為者にフォーカスを当てた座談会を進めていきたいと思います。
本日、進行を担当いたします、特定社会保険労務士の熊井弘子と申します。私は職場のハラスメントの第三者調査を専業としている社労士です。当学会のe-learningの「ハラスメントと法(実務編)」というのも担当しています。機会があればぜひ受講していただければと思っています。
さて、和田先生はメンタルヘルス、ハラスメントの問題に精力的に取り組んでおられまして、『最新パワハラ対策完全ガイド』などのご著書もたくさん出されています。和田先生ご自身より自己紹介と日頃の業務についてご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
和田
私は2011年にメンタルプラス株式会社を設立し、主にハラスメント防止やメンタルヘルス、キャリア支援を行っています。資格は公認心理師や1級キャリアコンサルティング技能士、シニア産業カウンセラー等を保有しております。支援先としては主に民間企業、特に大手企業、中小企業とも実績があり、東京消防庁消防学校でのハラスメント教育や警視庁、文部科学省での支援経験もあります。年間200回以上、トータルで3,500回以上のハラスメント防止、メンタルヘルス対策等の講演、研修を行った実績があります。その他、EAPや公益財団法人21世紀職業財団様の支援もさせていただいています。約3年前から札幌と横浜の2拠点生活を送り、札幌観光大使としても活動しています。
熊井
パワハラ関連はどのような活動をされていますか?
和田
パワハラ防止の講演や研修は多数実施していますが、その前後での個別相談やマネジメントコンサルテーション、行動変容を促す個別研修も行っています。特に新年度前に人事部からパワハラ的な管理職の行動変容を促すための個別研修の依頼が多い傾向です。4月からの新体制前に部下との関わり方を変えてほしいと3月末までの依頼が集中、特に自治体からの依頼は予算の関係でギリギリに来ることが多く、本当は2~3日かけて丁寧にやった方がいい人もいますが、私のスケジュールが埋まっている場合、短時間の研修に後日のフォローアップ面談という組み合わせで実施することが多いです。
熊井
まさに今日のテーマそのものという活動を日頃からずっとなさっているというところで、私たちもお話が聞けてうれしいなと思っております。先程の企業から依頼される個別研修での行動変容支援のお話をいただきましたが、他に行為者との接点はありますか?
和田
管理職自身が部下との関わりに問題を感じて相談に訪れることがあります。逆に、管理職本人は問題を認識していないが、部下から苦情が出ていて、人事部からの促しで相談を受けるケースも少なくありません。長年関わっている東京消防庁消防学校では、13年前から初級幹部研修を担当していて、署長、副署長、教官にも研修をする機会があります。パワハラにならない適切な指導、訓練のあり方等を今の時代に合わせて見直す方法を研修でお伝えしています。そういったところですかね。
熊井
和田先生、ありがとうございます。先生のご著書にもあるように、令和2年にパワーハラスメントが法制化されました。例えば、私が調査に行って、これがうちの会社のやり方だ、うちの企業文化ではこれは当然だという主張は良く出てきます。しかし、法に照らしてみて、外からどう見られるか。その視点を説明しやすくなったのが法制化後の変化の一つかなと感じております。
そして世の中、何ハラって幾つあるか分からないっていうぐらい、ハラスメントという言葉があふれている。調べもしないで勝手に自分の感覚で裁く人も多いと感じています。行為者とされた人の行動変容は取り組むべき最優先課題ですが、行為者1人をスケープゴートにして、間違った裁き方をしている時がないか注視すべきですし、懲戒ありきだけで良いのかというところも専門家としてきちんと見ていく必要があると思っています。
では皆さんからの質問に移ります。弁護士の小島先生お願いいたします。
<ハラスメント行為者とされた管理職の心理>
小島
弁護士として、ハラスメント行為者として調査を受けている個人から相談を受けることもあります。営業販売の中心人物や経営管理の番頭格の方について、部下たちからハラスメント被害のクレームが集中して会社の調査が開始されたりすると、ひどくショックを受けて、追い詰められることがあります。これまで会社のために尽力してきたにもかかわらず、ハラスメント行為者とされることで、会社から切り捨てられたように感じてしまう。解雇、降格などの危機に直面し、不安や心配にとらわれる状況になります。このようなハラスメント行為者の受け止め方や、今後への不安などについて、和田先生からコメント頂けるとありがたいなと思うのですが、いかがでしょうか。
和田
パワハラ防止法施行前後で、行為者の反応に変化があるのを感じています。施行前のパワハラ行為者は、ヒアリング段階で非を認めないことが多く、自己正当化や問題の矮小化が見られる傾向がありましたが、施行後は研修の増加や社会問題化により、非を認める行為者が増えました。ただし、非を認めても自分だけが悪者にされることに納得できない気持ちは変わらい人が多いため、支援者として、そのような気持ちとしっかり向き合うことが大切だと思っています。懲戒処分を受けた行為者にはショックを受けた人もいますので、メンタルヘルスケアは重要です。また、処分を受けたことでキャリアが変わり、自己価値を失ったと感じる人もいます。このような時、ブリッジスのトランジション理論に基づき、トランジションに適応する3つのステップを展開します。第1段階「終焉」の後、行為者は第2段階の「ニュートラルゾーン」で苦悩と混乱状態にあります。それを乗り越えて第3段階「開始」への移行を支援します。ハラスメント問題、メンタルヘルス、キャリアの視点から多角的に支援することが重要だと考えています。
小島
なるほど、キャリアの大きな転換点、移行する段階だと捉えていくわけですね。
和田
そうですね。元々パワハラする人は能力が高くて実績のある人が多く、職場に適応していた状態から不適応な状態になっていますので、そこから再適応するというアプローチを取っていきます。ロジカルだけだと心が反発しますので、行為者の方とは、情緒的に関わりながらも、合理的にしっかりと説明しながら進めていくと、だんだん前向きになっていただける方が多いです。
小島
和田先生の話し方、その口調そのものが、どんどん前向きに引っ張ってくださる感じです。
和田
ちょっと心がけております。
熊井
心がけ、素晴らしいですね。次は産業保健師の岡田先生です。
<全力で働いた結果がハラスメント?-管理職の葛藤と健康問題>
岡田
私のような医療職のところに相談に来る場合、ほとんどが、体調があまり優れないという形で関わることが多いです。私が関わったケースでは、お話を聞いていると、本人は会社に対する忠誠心も強く、期待に応えようと一生懸命にお仕事をなさっている管理職の方でした。その一生懸命さが部下に対するハラスメント行為者になってしまうという、本人にとって意図しない状況となり、ストレスを感じて体調を崩されたようです。このような場合の対応やアドバイスをお聞かせいただきたいです。
和田
メンタル面に気をつけながら、予防の観点から行為者のレジリエンスが高まるような支援を心がけています。「レジリエンス」という言葉では敢えて伝えないのですが、教育内容を実践していただければ、必然的にレジリエンスが高まるようになります。このレジリエンスが高くないと、また問題に直面した時に、自分の偏っている部分が、偏りを強めて問題行動となって表れてきますので、レジリエンス向上の支援は必要だと考えています。当然、企業の目標や重点に合わせて、行為者に適切なプランを設計することが求められます。行為者が自己改善を目指し、行動目標を設定して実行できるようサポートします。法令遵守の観点から企業側がハラスメントの措置義務を全く果たしていない場合は支援依頼を受けないこともあります。また、再発防止の実効性の観点から行為者が個別研修前の事前学習をしない場合は研修を行わないこともあります。
熊井
そもそもパワハラの行為者に支援が必要との概念に至ってない人もたくさんいると思うので、まず意識していきたいところですね。では、次は産業医の彌冨先生です。
<行為者支援が職場を変える>
彌冨
行為者への支援を通じて、組織文化や職場環境が改善した具体的な事例があれば、どのようなプロセスを経て実現されたのかをお聞かせください。私は、ハラスメントを意図的に行う人は基本的にいないと考えています。多くの場合、そうせざるを得ない背景があり、それを変えない限り、たとえ人が入れ替わっても根本的な問題は解決されないままです。そのため、背景要因へのアプローチについてもお伺いしたいと思います。また、特に行為者の1つ上の立場にいる、いわゆる上司の関わり方が、職場環境の改善にどのような影響を与えたのかについても、お聞かせいただければと思います。
和田
個人に行動変容を求めても職場環境が変わらなければ再発防止の実効性は上がりません。職場課題を抽出して改善することが必要であり、トップからのメッセージはとりわけ重要です。ハラスメント研修の冒頭、ある企業のトップの方が「この問題は経営課題として認識しています。私が責任者であり、私が先頭に立ち続けてこの問題を解決していく」と言ってくれたんですね。その時、社員の方が受け止めてくれた表情をしていました。その後、講師の私から、お互い対等のパートナーとして礼節を重んじ、相手が自分に無礼な態度を示したとしても、自分は相手に同調して無礼な態度を絶対に返さないということを丁寧に話していくと、受け入れてくれる参加者が多いんです。どのような職場で働きたいか、自分がどうのように関わって欲しいかは皆同じなんだと思います。悪いところをなくす努力をすると、みんな萎縮し始めるので、どうありたいかっていうところに目を向けて、良い職場環境をつくっていきましょうというアプローチのほうがより受け入れやすく共感してくれる、そのあたりを研修会でやるようにしております。
行為者の方との定期的な面談を一階層上の上司にお願いすることもあります。専門家の支援だけでなく、現場で再発防止を支援する取組みは改善に良い影響を与えた実際の事例があります。
彌冨
本当に真摯に向き合ってくれる経営者や人事、上司の方がいると、職場環境は良い方向に進むものだと、先生のお話を伺いながら感じていました。一方で、ハラスメントの行為者やその上司が二枚舌や、事なかれ主義を取る場合には、どのように対応し、改善へと導くべきだとお考えでしょうか。
和田
職場環境改善の必要性ははっきり言うようにしています。本当にやるつもりがあるのか、具体的にいつまでに何をやるのかと。改善を怠ると、後で深刻な副作用が来る、今職場改善した方が皆さんにとって良いと話します。実際に問題のある企業を例に挙げると、皆さん考え込むんですね。良い意味で逃げ場を与えないように関わるようには心がけています。
彌冨
ありがとうございました。とても参考になり、実践的なお話を伺うことができて良かったです。
熊井
トップの話が和田先生から出ましたが、まずトップが駄目だという姿勢を示していくというのは非常に重要なことで、本気で経営課題として取り組むということは必須事項だと私も思っております。でもトップがこの会社のことを全て知っていると思いこんでしまうのはリスクがあります。例えば新卒の若手のところに膝詰めで話を聞きに行って「何か問題があるか?」とやって「自分が全員に聞いたところ何も問題はなかった」と言い切ります。下の立場の人からあなたには言えないこともあるんですよ、というのがわからないわけです。ここは専門家として注意すべき点で、相談窓口の独立性の重要さにもつながります。
次はトップ自身の問題について岡田先生お願いします。
<トップのパワハラ、誰が止める?>
岡田
社長や経営層などのいわゆるオーナーと言われる方々が、明らかにパワハラをやっているだろうという場合でも、そこに指導が入ることはなかなかなく、場合によってはどんどん昇進することもあり、誰もがおかしいと思っても何もできない。特にオーナー企業の場合のハラスメントには誰も声を上げられないのではないかなと思いますが、そんな時はどのように対処していくのが良いのでしょうか。
和田
私もこの問題は対応に苦労してきました。オーナー企業のトップの方がパワハラしていると、その下のコンプライアンス室とか人事部ってほぼ機能しなくなって、そもそも調査もできないっていう状態になりますので、トップハラスメントが発生した場合、顧問弁護士の先生や社労士の先生、外部の専門家が面談することを社内ルールとして決めておくことをお勧めしています。人事部の本部長が社長に伝えにくいことを代わりに私が伝えることもあります。パワハラ社長はしばしば問題を矮小化したり、経営の厳しさを強調して反発することがあります。そのような状況でも決して引かずに、「この事態を解決するのは社長の義務であり、社長を支援するのが私の責務です。周囲が社長に同調して、今の状態がより悪い形で強調されると、これから立て直しが利かなくなります。」と社長より大きな声ではっきり伝えたこともあります。正論や専門性が通用しないとき、対人援助者としての信念で押し返します。オーナー企業のトップは自分の会社が大切ですから、長く続く良い会社をつくっていきましょうという角度から話をしていくことも大切だと思います。現場で問題を抱えずに専門家を含めたチームで解決することを提案するようにしています。
熊井
和田先生の体当たり、人間力によるところが多いという前提はありつつ、やはりプロフェッショナルの第三者がどう介入していくかっていうところは大切ですね。ちょっと雑談的にはなりますが、社長さんってお医者さん好きだから、お医者さんの言うこと聞いたりするんですよね。お医者さんの神通力はすごくて、他の人の言うことは聞かないのに「だって(医師の)彌冨先生がこう言ってた!森本先生がこう言ってた!」。 和田先生、そう思いません?
和田
(大いに頷きながら)いや、そう。そうですよね!ほんとにそこはあると思います。
熊井
お医者さんの神通力と言って良いかわかりませんが、せっかく学会なので、何かアウトプットできるもの、医療側、もう少し広く言うなら産業保健、そういうところからも何か和田先生のようなプロフェッショナルと一緒に組めていけるところがあったらと思います。勝手にドクターのお二方お名前使ってすいません(笑) どんな横暴な社長でも、お医者さんが言ったっていうのは聞く気がして、ここに絶対私はヒントがあると何十年も思っていて、まだ形にできてないのでやりたいなと思いました。横から余計なことを挟んでしまってすいません。
和田
いえいえ、私もやっぱりドクターのお力ってすごいなと思って。
熊井
絶対あると思いますね。
和田
オーナーとか、ものすごく怒鳴ってくる人もやっぱりいますから 。
熊井
いますね。
和田
大声で怒鳴ってくる人には、私は「この人は助けてほしいと思っているから怒鳴っている」と認識するようにしています。相手の反応を攻撃ではなく、援助希求ととらえることで、動じることなく相手と向き合える状況をつくります。自分が不安になったり、恐れを抱いちゃうと、そもそも支援者ではなくなってしまうんですよね。
熊井
そのように意識されているのですね。トップへの対応は、どこからいってもタフなものだと思いますが、せっかく違う専門職が集まっているので、対処法をいろいろ出していきたいなというふうに思いました。次は、産業医であり社労士の森本先生です。
<パワーを使わない管理職>
森本
パワーを使うっていう部分ってすごく難しいと思います。会社の上位者の人たちに「あなたはパワーを持っている。だからこそちゃんと使わないといけないんだよ」っていうのを知ってもらうにはどうすればいいんだろうなっていう点を考えています。アドバイスを頂ければと思います。
和田
例えば、A課長がパワハラをして懲戒処分を受けて一般的な再発防止の教育を受けると、多くの方は同じような行為はしなくなると。でも、A課長パワハラしなくなったけど、何か全然元気なくなっちゃったね、みたいになってしまうんですね。ですから問題行動をなくすだけでなく、行為者の強みに光を当て、その強みを活かす方法を考えるようにします。すなわち、パワーを仕分けして、不当なパワーは出力停止、健全なパワーは出力強化できるようにします。悪いところをなくす努力をするというよりも、良いところを増やす努力をしたほうが、良い部分が出るようになって、悪い部分が必然的に減るという行動療法の考え方も 大事にしています。
森本
ありがとうございます。では、優しい方というか、気付けば主任に、気付けば管理職になったけど、自分の力の使い方が分からない。ハラスメントはそういう人はまずしないんだけど、一方で指導がうまくいかないというか、指導をすることに躊躇するみたいな方に対しては、何かアドバイスがあったらうれしいなと思いながらお尋ねします。
和田
そもそも管理職教育もせずに管理職にさせることはできないということを私はお伝えしています。新任管理職研修とかそういうところをしっかりやって、そもそもマネジメントっていうことを定義する必要がある。パワハラしないことは上司の目標ではなく、成果を上げるのが上司の目標でありマネジメントの目標になることを理解していただきます。10年たってから教育してもかなり厳しいですよね。だから最初にやっていく。途中で支援する場合は、その人のパーソナリティや成熟度によってアドバイスや教育の内容が異なってきますので、状況を踏まえて対応していきます。
森本
ありがとうございます。
<ハラスメント行為者と向き合う難しさ-担当者への支援策>
熊井
次に私のようなハラスメント調査の専門職や社内の担当者の方も含め、行為者に正面から向き合う人たちへのアドバイスをお聞きしたいです。事実関係確認の聞き取りを丁寧にしても暴言暴行が止まらない、或いは、質問に回答せず他者への非難が続く。病のなせる業かもしれないという前提を置きますが、明らかな虚言や被害妄想をずっと訴える方というのもいらっしゃいます。もう一つ、私たちが怖いと思っているのは、聞き取りの対象者から「もう死んでやる」「もう終わりだ」と言われることで、これらは非常に大きなストレスや恐怖を感じることですが、担当者へのアドバイスやケアについて教えていただけますか。
和田
相談面談 担当者向けの研修を受けることが重要と考え、私もその教育を15年以上続けております。重要なのは構造化された相談の受け方を学ぶことだと思っています。個々の対応にはバリエーションがありますが、傾聴を維持することが重要です。この研修に参加した担当者からはポジティブなフィードバックをいただいています。もし自殺のほのめかしなどに直面してしまったら、事前に誰に相談するかを決めておく、場合によっては面談を終了する選択肢を持つことが大切です。専門家と連携できていないと協力を仰ぐこともできませんので、あらかじめ誰に相談できるのか、誰につなげるのかということも仕組み化していく必要があります。
熊井
教育が必要だということと、そしてフォローが必要だということは誰に対しても一緒ですね。ハラスメントに関わった関係者がまた二次被害的なストレスを感じてしまうことが生じていますので、私たち専門家はそこにも目を向けていきたいなと思いました。ありがとうございます。
では、弁護士の小島先生から最後に総括的な質問をお願いします。
<総括: 行為者支援の再考-カスハラ問題が示すもの>
小島
このたび伺っておりまして、行為者の支援とか研修というものから、ぐるっと回って、一般の社員が相手の立場を理解したり想像したりして、よりコミュニケーション上手になることにつながらないかなと思いました。カスタマーハラスメントがルール化される局面になってきましたので、いよいよ問題行動をする人の心理とか、どういう認知をしているのかみたいなことを理解できないといけない。相手にする人は、恐れも感じるでしょうし、腹も立つでしょう。おそらく、カスハラというものが、行為者の理解というものに、スポットを当てるきっかけになるんじゃないかと思うのですが。このあたり、和田先生から、全体総括として何か思うところ、お話しいただけますでしょうか。
和田
これはすごく難しいのと同時に向き合っていかなくちゃいけない部分だと感じています。カスハラも行為者の心理っていうのをしっかりと踏まえるのはもうまさにそのとおり。私は心理学とリスク対応と交渉学の3つを中心に教育をしていますが、行為者の心理をしっかりと踏まえることができれば、非常に優れたカスタマーサービスを提供することができると伝えています。カスハラに対する対処がうまくなったからといって、サービスが良くなるってことではないんですよね。その前の苦情とかクレームにいかに対応できるかっていうことがカスタマーサービスの充実となるので、そこに顧客心理とか顧客共感ですとか、その前の視点取得とかっていうのが関わってくるということを、今BtoCのビジネスをやっている方に話すと、結構良い反応が出てくるんですよね。これ答えになりましたかね。ちょっと私も迷いながらですが。
小島
いや、まさしく。日本産業保健法学会は、予防こそ多職種で取り組む必要があるということで活動しているわけですが、このたび、予防というものの神髄を聞かせていただいたような気がします。もちろんリスクマネジメントではあるのだけれども、強みを引き出すとか、より効果的なものを学んで獲得するとか、そういった学びや訓練というものがやっぱり必要なんだなというふうに理解いたしました。
和田先生、ありがとうございました。