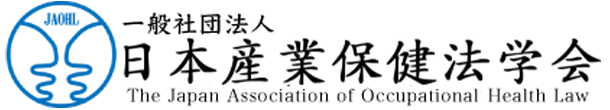【Q6】 私傷病による休職中の従業員が、新型コロナウイルスへの感染リスクを理由に休職期間満了後の休職期間の延長を求めて来た場合には、応じなければならないか?(Q6-1「休職期間の延長」)
一方、健常な従業員が、新型コロナウイルスへの感染リスクを理由に出社を拒否する場合、賃金減額等の不利益措置を講じてよいか?(Q6-2「出社拒否への不利益措置」)
A 感染リスクが大きく、復職可否の審査に支障がある場合などには、休職・復職制度の趣旨に照らし、または信義則(民法第1条第2項)上、休職期間の延長をする義務が発生する可能性があります(Q6-1「休職期間の延長」)。
同様に、感染リスクが大きく、従業員の欠勤に正当な理由があると考えられる場合には、出社拒否に対して不利益措置を講じることはできません(Q6-2「出社拒否への不利益措置」)。
これらの問題を検討する過程では、まずは感染リスクの分析・評価をどう行うかがカギとなります。新型コロナウイルスの感染リスクについては、未だ十分に信頼し得る医学的知見が定まっていない状況です。このような不明確なリスクに対処するにあたっては、感染リスクの分析・評価のための合理的なルールを策定し、公正に運用することが求められます。
【解説】
1.Q6-1「休職期間の延長」について
(1) 法の考え方
休職期間の延長とは、使用者が許容した休職期間が満了する時に休職事由が消滅しているとはいえない場合であっても、退職ないし解雇とはせず、休職の継続を認めることです。休職の延長は、従業員の同意があるときはもちろん、就業規則に根拠がなくても、使用者の裁量によって行うことができます(西濃シェンカー事件、東京地判平22・3・18労判1011号73頁)。
では、従業員から休職期間の延長を求められた場合に、使用者には、延長に応じる義務が発生することがあるのでしょうか。この点、就業規則に休職の延長の要件が明確に定められている場合は、それに従うことになります。
一方、就業規則に明確な定めがない場合であっても、使用者が定める休職・復職制度の解釈として、または信義則上、使用者側に延長に応じる義務が発生することはありえます。たとえば、使用者の責めに帰すべき理由による場合は勿論、やむを得ない事情によって、復職の可否に関し十分な判断が得られなかった場合や、産業医面接など復職に向けての手続が中断せざるを得なかった場合です。また、休職期間満了時に休職事由が消滅していないが、わずかな期間を待つならば、休職事由が消滅する可能性がある場合です。企業に設けられている病気休職制度の多くは、病気で働けない労働者に対して解雇を猶予するものであって、その事由が解消したことの証明責任は労働者が負うと解されており、現にそのことを就業規則に明記しているところもあるます。であれば、労働者自身は就労可能なのに、別の要因で働けないような場合、休職期間を延長するなど、その者の不利にならない対応をすることが、制度趣旨に適います。少なくとも、労使間の衡平に適うでしょう。
ただし、延長はあくまで例外的な措置ですから、無用に長くしないこと、従業員の要望も踏まえつつ、使用者側のイニシアチブで行うことに留意すべきでしょう。
(2) 感染リスクとの関係
新型コロナウイルスの感染リスクについても、そのリスクが大きい場合には、上記のやむを得ない事情に該当すると考えられます。感染リスクが大きく復職審査を行えない場合や、復職後の就業が困難な場合などです。
そのため、感染リスクの分析・評価がカギとなります。感染リスクの考え方は個人差が大きいので、使用者としては、従業員の納得を図り不安を払拭するためにも、合理的なリスクの分析・評価、感染予防の対策が求められます。
新型コロナウイルスの感染リスクについては、医学的なエビデンスの不足から不分明な点が多いといわれますが、使用者としては、法の考え方を踏まえた上で、感染リスクの分析・評価のための合理的なルールを策定し、公正に運用する必要があるでしょう。後に、感染リスクの分析手法の1つとして、3E分析を提言するので、ご参照ください。
(3) 具体的検討
本問でいえば、感染リスクから復職可否の審査自体に支障がある場合などは、感染リスクが低減するまで休職期間を延長する義務があるといえます。
緊急事態宣言が発令されたが、まだ職場の感染予防措置を準備できていない場合などには、まずは1月程度休職期間を延長し、その間に、適切な感染予防対策を行い、その上で、あらためて感染リスクの分析と評価を行って、休職期間満了や再度の復職期間の延長を検討するのが妥当でしょう。
一方で、そもそも感染リスクが小さく、復職可否の審査にも支障がない場合などには、延長に応じる義務はありません。この場合でも、従業員の不安感への配慮の観点からは、分析・評価をもとに、感染予防対策として講じている措置と感染リスクの程度について丁寧に説明することが望まれます。ただ、使用者が合理的な手続や配慮を尽くしたにもかかわらず、従業員が復職可否の審査に協力せず、休職期間満了時に休職事由が消滅しているとは判断できない場合は、原則に戻って退職ないし解雇となります。
2.Q6-2「出社拒否への不利益措置」について
(1) 法の考え方
労働契約上、従業員は、使用者の指示に従った労働をする義務を負います。
そして、出社拒否とは、無断欠勤と同義と解されます。判例上も、無断欠勤とは、届出はあるものの正当な理由があるとは認められず、使用者が承認しない欠勤も含む旨を述べたものがあります(炭研精工事件・最判平3・9・19労判615号16頁)。無断欠勤に対しては、使用者の責めに帰すべき事由によらず労務が提供されない場合として、従業員には賃金は支払われないのが原則です(ノーワーク・ノーペイの原則)。
では、これを超えて、無断欠勤に対して、減給等の懲戒処分が許容されるでしょうか。
通常の就業規則には、懲戒処分事由として「無断欠勤が一定期間に及んだ場合」が定められていますので、無断欠勤に正当な理由がなく企業秩序違反レベルに至った場合は、懲戒処分ができます。ただし、この場合もいきなり賃金減額等の重い懲戒処分をするのは相当でなく、注意指導、警告、そしてけん責等の軽めの懲戒処分をするなどして、改善の機会を与えるべきです。
他方、無断欠勤に正当な理由があれば、懲戒処分等の不利益措置を講じることは許されません。たとえば、私傷病としてのメンタルヘルス不調の疑いがある社員の欠勤に対しては、直ちに懲戒処分をするのは不適切であり、まずは病状把握が求められます(日本ヒューレット・パッカード事件・最判平24・4・27労判1055号5頁)。
また、そもそも、従業員の生命や身体に予測困難な危険をもたらす命令は無効であり、従業員を拘束しませんので(千代田丸事件・最判昭43・12・24民集22巻13号3050頁)、勤務することで予測困難な危険が発生するような場合は、業務命令として出勤を命じることはできません。
(2) 感染リスクとの関係
新型コロナウイルスの感染リスクについても、そのリスクが大きい場合には、無断欠勤の正当な理由に該当したり、そもそも出勤命令が無効になったりする可能性があります。感染リスクの分析と評価については、前記のとおりです。
(3) 具体的検討
本問でいえば、緊急事態宣言が発令されている場合や職場の感染予防措置が不十分なため、感染リスクが大きいと考えられる場合に、無断欠勤に正当な理由があるといえ、懲戒処分等の不利益措置は許されないでしょう。
他方で、市中感染が減少傾向で使用者も適切な感染予防措置を行っているなど、感染リスクが小さい場合には、無断欠勤の正当な理由はないといえます。ただし、この場合でも、分析・評価にもとづき感染リスクが小さいことを丁寧に説明して、従業員に出社を求めることが大切です。
懲戒処分は、感染リスクが小さく、かつ使用者が感染リスクの分析評価、その結果を踏まえた真摯な説明、安全配慮などの合理的な手続を尽くしたにもかかわらず、従業員が過剰な感染リスク不安を訴え続け、無断欠勤を繰り返す場合などに限るべきです。なお、過剰な感染リスク不安の背後にメンタルヘルス不調が疑われる場合は、前記ヒューレット・パッカード事件のとおり、直ちに懲戒処分をするのではなく病状把握に努めなければなりません。
3.手続的理性とリスク分析・評価
(1) 合理的ルールの策定と公正な運用
上述のとおり、法的な考え方を踏まえると、感染リスクの分析・評価をどう行うかがカギとなります。多くの労働事件の裁判例でも、使用者側が合理的な手続を履行したか否かが、その過失の判断に際して重視されているため、合理的ルールの策定と公正な運用という手続的理性の視点で対応することが必要です。
コロナの感染リスクについての医学的エビデンスが不足していたとしても、産業保健スタッフや人事労務担当者など関係当事者のコンセンサスにもとづいて、合理的なルールを策定して公正に運用をすることは可能です。
(2)リスク分析モデル試案
手続的理性の視点からリスク分析のルールを考える際、たとえば、従業員(Employee)、外部環境(Environment)、使用者(Employer)の3つの視点から情勢を俯瞰し(仮に「3E分析」とします)、リスク要素の漏れがないように議論してリスクの洗い出しを行うことが有効と思われます。
3E分析では、従業員のリスク要素として、基礎疾患、年齢、妊娠等の健康情報やライフスタイルが挙げられます。また、外部環境のリスク要素としては、緊急事態宣言の有無や市中感染状況等が、使用者のリスク要素としては、感染の可能性が高い業務か、感染予防対策の有無等が考えられます。以上は例示であり、3視点(項目)のリスク要素には、多種多様なものが存在します。
3項目のリスク要素を洗い出した上で、図表「感染リスクの3E分析」のように項目ごとのリスク点を評価します。

そして、リスク評価点合計3点以下を「感染リスク小」、4~5点を「感染リスク中」、6点以上を「感染リスク大」として扱うルールとすれば、本問との関係では、「合計8点で感染リスク大のため、休職期間の延長を可とする。」や「合計3点で感染リスク小のため、無断欠勤の正当な理由とは認めない。」などの判断が可能です。
上記リスク分析に加えて、必要に応じて個々のケースの責任分析をすることも考えられます。本問との関係では、「合計5点で感染リスク中だが、安全配慮義務違反の責任を問われる可能性があり、使用者リスク点が3点と高いので、感染予防対策が完了するまで休職期間の延長を可とする。」などの一定の方針を導くことができるでしょう(ただし、新型コロナウイルスの感染については、リスク判断以上に責任判断は困難です。責任分析をして従業員に不利な措置をする場合はとくに労務リスクが発生しやすいことに留意すべきでしょう。)。使用者視点のリスクには、法的リスクのみならず、感染者が生じることによる風評被害(たとえば、食品製造加工業者の工場労働者に感染者が生じた場合をイメージして下さい)などの経営上のリスクを含めて考えることもできるでしょう。
3E分析は一試案であり、感染可能性のリスクと感染による重症化リスクをも区別していない荒削りなフレームワークですが、使用者が安全配慮義務を果たすためのツールにもなると思われます。個々の職場等で、活用方法を試行錯誤して頂き、、改善提案等をフィードバックをいただけたら幸いです。
4.おわりに
感染リスクの分析・評価に一律の正解がないように、使用者の安全配慮義務についても、どの程度の感染予防対策が求められるかの一律の正解はありません。
業態や職場によって感染予防対策は異なる部分がありますので、まずは感染リスクの分析と評価を行い、リスク要素を洗い出した上で、可能な感染予防対策を実践していくことが必要です。感染リスク低減のための体制を含めた手続の整備こそが、安全配慮義務の履行と評価できるでしょう。
感染リスクの問題に留まらず、産業保健の現場に唯一の正解はありません。法の考え方を踏まえた上で、多職種が連携した産業保健活動によって、合理的なルールを策定し公正に運用していくことが求められています。
以上
(参考文献)
1.杜若経営法律事務所「新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A(ver.3)」Q4
https://bit.ly/3fLyMt2
2.日本労働弁護団「新型コロナウイルス労働問題Q&A(ver.2)」Q2-5、9-3
http://roudou-bengodan.org/covid_19/
※1)は使用者側、2)は労働者側の視点から書かれていますが、いずれの立場でもリスク分析と評価を重視していることは共通です。手続的理性の考え方のもと、リスク分析と評価を誠実に行うことが、労使の対話の糸口となると考えられます。
産業保健法学における手続き的理性(合理的な手続を設定し、公正に運用することを通じて、理性と良識を示すこと)の重要性については、三柴丈典「休職・復職判定における課題について」産業保健21、66号4-6頁(2011年)が提唱した。その重要性を説いた最近の著作には、三柴丈典「産業医制度はなぜ必要なのか~働き方改革関連法の施行を踏まえて改めて考える~」DIO(連合総研レポート)33巻5号4-5頁(2020年)などがある。
〈執筆者〉
井上 洋一(愛三西尾法律事務所・弁護士、中小企業診断士、産業保健法務主任者)
【要点補論(2023.4.5追記)】
1 使用者は、安全配慮義務(労働契約法5条)として、労働者が就労するに当たり、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため通常求められる感染防止策を講ずる義務があります。必要とされる感染防止策の具体的内容は、その時々のウイルスの特性に関する医学的知見、当該労働者の職種、担当業務の内容、職場環境等の具体的状況により異なりますが 、職場における感染リスクのアセスメントを実施し、その上で安全衛生委員会、衛生委員会等における調査審議や労使協議等を踏まえて、当該職場における具体的な対策を決定することが望ましいでしょう。
使用者が必要な感染防止策を講じている場合、労働者が感染リスクを理由に出社を拒否することは、生命・身体に重大な危険が具体的に存在するような状況でもない限り、基本的に労働義務の不履行となり、これに対応する賃金の支払義務はありません。
他方、使用者が必要な感染防止策を講じておらず職場環境が感染リスクの高い状況のまま改善されていない状況で、これを理由に労働者が出社を拒否する場合には、使用者の出社命令は業務命令権の濫用に当たり、違法無効とされる可能性があります。この場合、使用者の責めに帰すべき事由による労務提供不能となり賃金支払を拒絶できないとされる可能性があります。
2 なお、労働者が在宅勤務を要求した場合の対応については、Q2をご参照ください。
〈執筆者〉
吉田 肇(弁護士法人天満法律事務所、弁護士、元京都大学客員教授)
鈴木 悠太(弁護士法人天満法律事務所、弁護士)