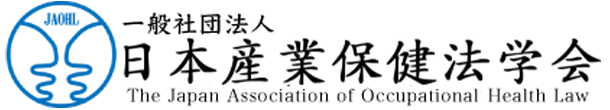Q2 新型コロナウイルス流行に伴い会社が「従業員は原則在宅勤務」を決定したところ、メンタルヘルス不調により長らく休職していた従業員が在宅勤務での復職を希望した場合、会社は当該従業員の復職を許可すべきでしょうか?
A 基本的には経営判断によりますが、その判断をルール化して周知する必要があります。
すなわち、復職判断は、雇用契約上本来果たすべき業務(債務の本旨に従った履行)を果たせるようになったか否かによりなされます。具体的には、①休職前に就いていた業務を果たせるようになった場合、②2-3ヶ月の就業上の配慮(業務軽減等)を経れば、休職前に就いていた業務を果たせるようになった場合、③雇用契約上配置可能性がある他の業務のうち遂行可能なものを労働者が申し出て、労使間で調整可能な場合、の3種類になります。しかし、いずれも、雇用契約上本来果たすべき業務を遂行できることを前提にしています。よって、事業者が、在宅勤務をあくまで新型コロナに対応するための一時的、臨時的な勤務であり、雇用契約上の本来業務ではないと位置づけるのであれば、それを遂行できるからといって、復職を認める必要はありません。本来の雇用とは別の臨時雇用として、それに応じた処遇をすれば問題ありません。また、在宅勤務では、復職後の経過観察が難しいので、在社勤務の場合よりも、若干復職条件を引き上げることもできるでしょう。ただし、在宅勤務の位置づけをルール化して労働者に周知する必要があります。また、業務の実質が本来業務と変わらない場合や、在宅勤務が定常化するようであれば、話が変わってきます。
【解説】
1 傷病による休職から復職するための要件として、多くの事業者の就業規則では、「従前の職務」を通常の程度に行うことができる健康状態に復していることを求めています。
「従前の職務」について、最近の裁判例(片山組事件(最一小判平成10年4月9日労働判例736号15頁)、独立行政法人農林漁業信用基金事件(東京地判平成16年3月26日労働判例876号56頁)、日本電気事件(東京地判平成27年7月29日労働判例1124号5頁)等)の傾向を踏まえると、その労働者が休職前に従事していた職務だけを基準として能力回復の有無を判断することは適当ではなく、その労働者が雇用契約上求められている本来の労務提供を基準として復職の可否を判断することが適当です。これは、休職前に従事していた職務以外に遂行可能な職務がある労働者にとっては、復職可能性を広げることになりますが、逆に、そもそも休職前に従事していた職務が、雇用契約上本来遂行すべき業務ではなく、能力不足などのため、特別な配慮のもとに割り当てられていた職務であったような場合、たとえその職務を遂行可能な状態に快復しても、復職を認める必要はないことになります(上記独立行政法人農林漁業信用基金事件東京地判 )。
2 当然ながら、復職のし易さは、労働者の契約上特定された/配置可能な職種にも左右されます。専門的な知識や職人的な技能によって自分のペースで黙々と取り組めるような職務であれば、通勤の負担や人間関係の煩わしさがない在宅勤務であれば、メンタルヘルスに多少の懸念があったとしても職務を遂行できるかもしれません。他方、上司や同僚と必要なコミュニケーションや協力・連携しての作業をすることが求められる職務であれば、たとえ在宅勤務であったとしても、メール、電話、Web会議等を駆使して、オフィスでの勤務にも増して効率的・効果的に意思疎通をとらなければならないため、メンタルヘルスの回復が、より一層求められるかもしれません。
また、労働者のメンタルヘルス不調の性格や程度も影響を及ぼすでしょう。例えば、通勤や職場での感覚過敏による苦痛が就労の支障になっていたのであれば、そのような苦痛がない在宅勤務の方が、むしろ復職し易いかもしれません。一方、上司や同僚とのコミュニケーションを適切にとれないことでストレスを抱えてメンタルヘルス不調になっていた経過があれば、その根本問題が究明され、適応できる見込みが立たない限り、復職させるのは危険かもしれません(ただし、疾病休業の趣旨からは、原則として、臨床症状が改善すれば、復職させ、職務能力等にかかる根本的な問題には、復職後の労務の評価によって対応すべきことになります)。
3 以上の通り、事業者は、雇用契約上本来果たすべき業務の範囲で、労使間にて調整できる業務が現にあれば、当該労働者を復職させることになりますが、在社勤務の場合より復職後の経過観察が難しいため、復職計画で克服すべきハードルをやや高めに設定することは、たとえ司法審査に付されても、合理的と認められるでしょう。
以上
(参考文献)
三柴丈典.休職法と法~一律的な判断基準に代わるもの~⑺:産業医学ジャーナル.43⑶.2020.
〈執筆者〉
淀川 亮(弁護士法人英知法律事務所・弁護士)
小島 健一(鳥飼総合法律事務所・弁護士)
三柴 丈典(近畿大学法学部・教授)
【要点補論(2023.4.5追記)】
第1 メンタルヘルス不調を患った労働者のテレワークによる復職の可否の判定に当たっては、①テレワークの場合は本人の観察が難しく健康管理に困難を伴うこと、また②そもそも労働契約とは労働者を指揮命令下に置くことが本質の一つであり、労働者側の事情で配置や職務の割当てを含めた業務命令を制限されるのは本末転倒ともいえること等の観点から、使用者側としては慎重な姿勢を示す場合が多いでしょう。一方で、労働者も人間である以上、常に万全のパフォーマンスを期待することができないことは労働契約上の前提とされていると解されますし、近年は障害者雇用を支援する法整備が進んでおり、障害のレベルを問わず、合理的配慮(障害の性格や障害者の個性を踏まえた可能な限りの就労支援)が求められます。
以上を前提とすると、メンタルヘルス不調を患った労働者のテレワークでの復職に際しては、まずはテレワークと在社勤務のハイブリッドを採用して就業可能性を見極めるという方策を検討するのが適当でしょう。
第2 また、設例のような休職者に対する復職判定の場面を離れて、新型コロナウイルス感染症の流行を理由に、労働者が在宅勤務を要求し、出社を拒否した場合、会社は当該労働者に対して在宅勤務を認める必要があるのでしょうか。
1 国内法上、在宅勤務の請求権を認める法律は存在しません(2023年3月現在)。また、会社が就業規則等により在宅勤務に関する規定を置いている場合にも、通常は在宅勤務を認めるか否かについて会社の裁量を認める内容となっており、このような場合、原則として労働者に在宅勤務の請求権は認められず、会社に在宅勤務をさせる義務はないと考えられます。
2 一方、基礎疾患を有する労働者が障害者雇用促進法2条の「障害者」に該当する場合は、同法36条の3に定める合理的配慮措置(使用者に対して「過重な負担」とならない程度)を講ずる義務があり、別途の検討を要します。基本的には、まん延しているウイルスの感染力や病原性等の特性、労働者の症状の程度、職場や通勤における感染防止対策の内容等を踏まえて、出社させた場合の感染・重症化リスクの程度を評価するとともに、業務遂行上・労務管理上の支障の観点等も考慮しながら、在宅勤務を配慮措置として講じることの適否を検討する必要があると考えられます。例えば、出勤により感染するリスクが高くない場合で、在宅勤務中に連絡が取れない事態が頻発し改善も見られないといった、在宅勤務が労務管理上支障のある者については、在宅勤務を認めることが使用者に「過重な負担」を求めるものとして、そのような措置を講じる義務を負わないとされる場合があるでしょう。
合理的配慮措置を講じなかったとされる場合は、不法行為として損害賠償責任を負うとされる可能性がありますし、就業規則等に在宅勤務に関する規定を置いているときは、在宅勤務を認めないことは使用者の裁量権の濫用となり、労働契約上在宅勤務を認める義務があるとされる余地もあるでしょう。
3 なお、会社側が、新型コロナウイルス感染症の流行を理由に在宅勤務を命ずることの有効性に関しては、自宅という私生活上の空間を勤務場所とすることから、その有効性の要件については見解が分かれています。いずれにせよ、在宅勤務を命じる場合には、労使の協議や在宅勤務に関する規定の整備を行う等の手続を経るとともに、在宅勤務時の労働時間管理や秘密保持、在宅勤務に伴う費用負担、労働者のメンタルヘルス対策等の健康配慮に留意して運用することが望ましいでしょう。
(参考文献)
河野奈月「テレワークと労働者の私生活の保護」法律時報増刊新型コロナウイルスと法学(2022)
三柴丈典「大学勤務者のメンタルヘルスと法~実務的な対応法を考える~」大学のメンタルヘルス(近刊)
〈執筆者〉
吉田 肇(弁護士法人天満法律事務所、弁護士、元京都大学客員教授)
鈴木 悠太(弁護士法人天満法律事務所、弁護士)