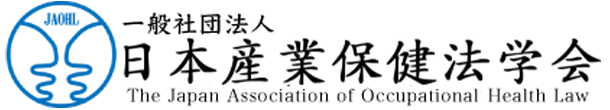多職種ディスカッション『従業員の【孤立防止義務】?地裁と高裁で判断分かれる』
井上(司会進行)
職場での「孤立」に企業はどこまで対応すべきなのか――。地裁と高裁で判断が分かれた今回の判決をもとに、弁護士の小島先生、産業医の五十嵐先生、社労士の熊井先生にお話を伺います。
まず、(地裁)千葉地判令和4年3月29日、(高裁)東京高判令和5年6月28日について、事案の概要と裁判所の判断をご紹介します。
- 事案の概要
本件は、被告(控訴人)と労働契約を締結し、テーマパークの出演者として就労していた原告(被控訴人)が、上司や同僚からパワーハラスメント(パワハラ)や集団的ないじめを継続的に受け、精神的苦痛を被ったと主張し、被告に対し、労働契約上の安全配慮義務違反もしくは不法行為、または使用者責任に基づく損害賠償を求めた事案です。
原告は、総額330万円(慰謝料300万円、弁護士費用30万円)および遅延損害金の支払いを求めました。
原告が主張した主な出来事は以下の通りです:
- 2013年2月7日のゲストからの暴行被害:
- パーク内でゲストから右手の指を曲げられる暴行を受けました。
- 直属の上司であるAスーパーバイザー(SV)および50歳代の男性上司から、「エンターテイナーなのだから我慢しなければならない」「心が弱い」と言われ、労災申請への協力を拒絶されたと主張しました。
- 上司からのパワハラ:
- B SVが、過呼吸の症状が出る配役の変更を申し出た原告に対し、「わがままには対応できない」「解雇対象になる」と発言した。
- C SVが、バックステージで過呼吸を繰り返す原告に対し、「次に倒れたら(役を)辞めてもらう」と発言し、配役の変更は「会社判断」であると述べたと主張しました。
- 同僚からの集団的ないじめ:
- Fが、ロッカールームで原告に対し、「やる気のないやつは全力でつぶす」「神様に嫌われているから絶対怪我する」などと発言した。
- Dユニットマネージャー(UM)が、職場の懇親会で原告に対し、「20代を集めてこい」「目障りだからどけ」「病気なら死んじまえ」「30歳以上のババアはいらねーんだよ、辞めちまえ」などの人格否定的な発言をした。
- E SVが、トイレで過呼吸になった原告に対し、「体調悪いなら早く言ってくれないと」「ショーがキャンセルになったらどう責任を取るつもりなのか」と発言した。
- Gが、楽屋で原告に対し、「バカ?」と罵倒したり、衣装の着用順を間違えそうになった際に大声で嘲笑した。
- Hが、休職からの復帰後、原告の業務制限について「私もできないとかいってみたいわー」と嘲笑したり、クリーニングに出される衣装について「最初から分かってたのに言わなかったんでしょー。意地がわるーい」と執拗に責め立てた。
- Iが、楽屋で原告に対し、「早くその大きなお尻をどかしてくれます。本当に邪魔」と発言したり、新人に原告の助言を聞かないよう促した。
原告はこれらの行為により、うつ症状を発症し、過呼吸の症状が出るようになったと主張しました。
- 裁判所の判断
この事案は、まず千葉地方裁判所で審理され、その後東京高等裁判所で控訴審が行われました。
- 千葉地方裁判所の判断(令和4年3月29日判決)
千葉地方裁判所は、原告の主張する個々のパワハラやいじめの発言の多くについては、事実として認められないか、あるいは社会通念上不相当とまでは言えないと判断しました。
しかし、裁判所は、被告が労働契約上の安全配慮義務を負っており、その一環として「職場の人間関係を調整する義務」を負っていたと認定しました。具体的には、以下の事実を指摘しました:
- 原告はゲストからの暴行被害後、うつ症状や過呼吸の症状を発症したものの、翌年度の契約更新に影響することを考慮し、できる限り人に知られないようにしていたこと。
- 医師は休職を勧めたが、原告は就労継続を希望していたこと。
- 原告が過呼吸の症状が出るようになったことで、配役について希望を述べることが多くなり、他の出演者から不満を持たれる者が増え、原告が職場において孤立していたこと。
- 被告の出演者雇用契約が、自動更新ではなく、オーディションや評価によって契約更新が決まるため、出演者間の人間関係が潜在的に競争関係にあり、軋轢を生じやすい性質があること。
- 原告の状況は、遅くとも2013年11月から12月の面談により、被告のマネージャーの知るところとなっていたこと。
これらの事実から、千葉地方裁判所は、被告は「他の出演者に事情を説明するなどして職場の人間関係を調整し、原告が配役について希望を述べることで職場において孤立することがないようにすべき義務」(以下、「孤立防止義務」)を負っていたと判断しました。
そして、被告がこの義務に違反し、職場環境を調整しないまま放置したことで、原告は周囲の厳しい目にさらされ、著しい精神的苦痛を被ったと認定し、被告に損害賠償義務があるとして原告の請求を一部認容しました。 賠償額は、慰謝料として80万円、弁護士費用として8万円の合計88万円とされました。
- 東京高等裁判所の判断(令和5年6月28日判決)
東京高等裁判所は、千葉地方裁判所の判断を覆し、原告の請求を全面的に棄却しました。
主な判断理由は以下の通りです:
- 個々のパワハラ・いじめの事実について:
- 地裁と同様に、原告が主張する個々の発言のほとんどは、証拠上認められないか、または仮に発言があったとしても社会通念上不相当とまでは言えないと判断しました。
- 特に、原告が録音したとされる会話データについても、発言の断片を意図的に切り取ったものにすぎず、文脈に照らせば違法ではないとしました。
- 原告の負傷の程度や、過呼吸に関する供述の一貫性にも疑問を呈しました。
- 原告の主張する「カースト」の存在も否定しました。
- 「孤立防止義務」違反について:
- 東京高裁は、原告が訴訟において、この「孤立防止義務」違反自体を明確に主張していなかったと指摘し、地裁の判断は処分権主義および弁論主義に反する違法なものであると判断しました。
- 仮に、原告の主張に「孤立防止義務」違反が含まれると解釈できたとしても、その義務の内容が抽象的すぎて特定されておらず、義務違反を認める根拠とすることは相当ではないとしました。
- さらに、たとえ義務が具体的であったとしても、原告が「義務を履行しなければならない程度にまで職場において孤立していた」とは認められないとしました。原告自身が産業医との面接で「具合の悪いことを知ってくれている出演者が徐々に増えている」と述べていたことなどから、孤立の事実を否定しました。
- 「仕事内容調整義務」違反について:
- 原告が控訴審で新たに主張した「仕事内容調整義務」違反についても、これは新たな請求に当たり、手続き上の問題があると指摘しました。
- また、内容としても、医師が特定の配役を止めるよう指導した事実はなく、原告が積極的に上司に過呼吸の状況を伝えていた事実も認められないことなどから、義務違反は認められないと判断しました。
結論として、東京高等裁判所は原判決を取り消し、被控訴人(原告)の請求を棄却しました。
最初に、「孤立防止義務」の有無や企業の法的責任の範囲等について、小島先生いかがでしょうか。
小島(弁護士)
「孤立防止義務」という新しい概念
地裁判決と高裁判決の全文を通読してみましたが、「孤立防止義務」という耳慣れない概念が、たしかに新しいものとして浮かび上がっています。一審の地方裁判所は、この孤立防止義務に被告が違反したとして、損害賠償責任を認め、慰謝料の支払いを命じました。
控訴審における処分権主義違反の評価
これに対し控訴審の高等裁判所は、「そもそも原告は一審でそのような主張をしていなかった」として、一審判決を処分権主義に反するものと評価したようです。処分権主義とは、民事訴訟における裁判所は当事者が申し立てた事項(訴訟上の請求)についてのみ判決することが許されるという原則であり、高裁はその点で「地裁がオーバーランした」と評価したようです。この点は、法律家でないと分かりづらいかもしれません。
「孤立」はどのような法的利益か
法律論として純粋に考えたとき、「孤立」という状態は一体何なのか、という問題があります。被告側が地裁判決に異論を唱えたのは、地裁が被告に帰責した原告の「孤立」とは、安全配慮義務で保護する利益とは別の何らかの人格的利益ではないのかという違和感からではないかと推測されます。その結果、高裁は、地裁が原告の主張していない請求について判断を下したのはおかしいとして、問題視したわけです。
実務の視点:孤立と職場のメンタルヘルス
しかし、産業保健や人事労務の現場を日常的に見ていると、パワハラの有無とは別に、職場内で孤立してしまっている労働者の存在にしばしば直面します。本人の心理状態や経緯には多様な事情があるにせよ、「孤立」という状況がメンタル不調の原因または結果となっているケースは多く見受けられます。
安全配慮義務の一環としての位置づけの可能性
こうした現実を踏まえれば、「孤立」は従業員の安全・健康への影響と無関係ではなく、安全配慮義務の一環として保護されるべき利益であると捉えることも、理論的には十分可能なのではないでしょうか。むしろ今後は、安全配慮義務の中に「孤立の防止」やそのための「人間関係の調整」も包含され得るという理解を進めていく余地があると感じます。
五十嵐(産業医)
因果関係の難しさ──「孤立」は原因か、結果か
「孤立が原因なのか結果なのか」は、実務上でも非常に難しいところです。孤立した、という事実が、メンタル不調の「原因」なのか、それとも何らかの出来事による「結果」なのか。この因果関係は簡単には割り切れません。
「主語は誰か」「主観的かどうか」の判別も困難
「孤立」という言葉を使うとき、誰の視点で「孤立」とみなしているのかという点も重要です。他者がその人を”孤立していると捉えている”ことと、本人が“孤立と感じている”ことが一致しているとは限らず、そこには主観と客観のズレが生じることもあります。
初めて聞いた「孤立防止義務」という言葉への戸惑い
私も「孤立防止義務」という言葉を今回初めて耳にして戸惑いを感じました。パワハラ防止法にある「人間関係からの切り離し」と関係しているのか、それとも安全配慮義務の解釈の拡張なのか分からないのが率直な感想です。
拡大解釈と一人歩きへの懸念
この言葉が変に拡大解釈されて、社会の中で一人歩きしてしまうのではないかという懸念もあります。今後、実務や判例の中でどのように扱われていくかは慎重に見ていく必要があると強く感じました。
熊井(社労士)
「孤立」という言葉の定義と背景の複雑さ
五十嵐先生のお話にも重なる部分ですが、「孤立」とは何か、そもそもの定義も大切ですし、それに至る要因や経緯についても、丁寧に見ていかないと実態がつかめないことが多いと感じます。
単に「孤立」という言葉だけが一人歩きしてしまうと、現場にとっても企業にとっても、非常にリスクが高いと感じました。
主体は誰か? 不快に思っているのは誰か?
また、孤立に関しては「主体」という視点も重要です。孤立という“行為”の主体が誰なのか、あるいは“不快に思っている”のは誰なのかという点は、意外と見落とされがちですが、非常に難しい問題だと思います。
孤立していると見られる本人が、実はそれを不快に感じていないケースもありますし、周囲が気にしていても本人は意に介していないこともある。このギャップがあるからこそ、評価や判断が非常に複雑になります。
就業環境の配慮とその「範囲」の不明確さ
就業環境について配慮すべきという点については、私も専門職として当然だと思っています。ただ、その「就業環境」とは何を指すのか、その範囲がとても曖昧だと感じています。特に今回の事案のように、「好きなことを仕事にしている人たち」が集まっている場面では、仕事への情熱と無理の境界が曖昧になるケースもあるのではないでしょうか。
線引きの困難さと今後の課題
結局、就業環境というのは、企業や個人の捉え方によって大きく異なり、どこかで線引きできるようなものではないというのが、率直な第一印象です。今後、こうした概念を法的にどう整理していくのか、また現場でどう扱うかは、引き続き大きな課題だと感じました。
小島(弁護士)
社会的な「孤立」と職場での「孤立」は別の問題
そうですね。たしかに、孤立や孤独が人の健康に影響を及ぼすということや、社会全体として孤立・孤独にもっと関心を持つべきという流れはあると思います。ただ、それと職場における「孤立」は少し別の文脈で捉える必要があると感じています。
密な人間関係の中で生じる「孤独」の複雑さ
職場って、実際には人と人との距離が近くて、チームで協力しながら進めていく、むしろ密な人間関係の中にあることが多いですよね。
その中で「孤独を感じる」「孤立してしまう」というのは、実はかなり難易度の高い現象というか、経緯も含めて一筋縄ではいかない問題だと思います。
「孤独」や「孤立」に対する個人差の大きさ
心理的な孤独の感じ方にも大きな個人差があります。人からどう見られているかをあまり気にしないタイプの人もいれば、逆に他人の目を非常に気にして不安を強めてしまう人もいる。
誰にとって「不快」なのか、「不安」なのか、それを誰の主観で測るのかという点も非常に難しいところです。
孤立は「される」だけでなく「する」側面もある
また、孤立というのは一方的に「される」ものではなく、自分から周囲との関係を拒絶してしまうケースもあります。あるいは、周囲が「この人はちょっと怖い」とか「なんとなく距離を取りたい」と感じて関係を避けることもある。
そういった経緯や背景があって、結果として孤立が生まれている場合も多く、非常に抽象的で捉えにくい概念だと感じます。
「職場環境調整義務」としての整理が妥当では?
こうした複雑さを踏まえると、一般論としては、やはりハラスメントの文脈で確立してきた「職場環境調整義務」という枠組みで整理するのが現実的ではないかと思います。これはセクハラ被害などを通じて裁判所でも認められてきた義務で、企業は職場環境について一定の配慮義務を負っています。
処分権主義違反とまでは言えないのでは?
ですので、今回の一審判決も、たとえ原告が明確に「孤立」を主張していなかったとしても、安全配慮義務や職場環境調整義務を根拠に裁判所が判断したのであれば、処分権主義に違反しているとは言えないんじゃないか、というのが私の見方です。
「孤立防止義務」を独自に立てたわけではない?
実際、地裁の判決文を見ても、最後の結論部分で「被告は他の出演者に事情を説明するなどして職場の人間関係を調整し、原告が孤立しないよう注意すべき義務を負っていた」と述べているに過ぎません。
これは「孤立防止義務」という新たな独自義務を創設したというよりも、あくまで人間関係を調整する目的の一つとして「孤立を防ぐ」ことが挙げられたに過ぎないのではないか、と読むこともできると思います。
人間関係の悪化の具体的な一例としての「孤立」
つまり、「孤立防止義務」という言葉に注目が集まりすぎていますが、本質的には安全配慮義務の中の人間関係調整義務という枠組みの中で、孤立という現象が具体的にどう扱われるかという問題にすぎないのではないでしょうか。
そういう意味では、今回の地裁判決が特に新しい概念を立てたというよりも、既存の枠組みの中で判断したと読むのが自然だと感じます。
井上(司会)
ではここで、「孤立」や「孤独」について、健康への影響や、産業保健職としてどう気づき、どう関わるべきか等について、五十嵐先生に医学的な見地からのお話をいただきます。
五十嵐(産業医)
まずは「孤立」の定義が重要
まず何より大切なのは「孤立」という言葉の定義です。言葉が変に一人歩きしないよう、定義を丁寧にしておくことが前提だと思います。
健康との関係は「類似概念」で考える
「孤立」が健康にどう影響するかという研究はあまり多くありません。
近い概念として「孤独(loneliness)」や「社会的孤立(social isolation)」があります。たとえば高齢者の孤独は、社会的ネットワークやソーシャルキャピタルが不足している状態とされ、健康に影響するというエビデンスはあります。
また、コロナ禍の在宅勤務に代表されるように「社会的孤独」も健康に悪影響を及ぼす研究があります。
加えて「主観的健康感」という概念、つまり本人がどう感じているかも孤立と近いと思います。主観的に孤立を感じていることが、主観的健康感を下げる可能性があると思います。
職場での「孤立」はいじめ・人間関係不良と混同しやすい
この事例のように職場での「孤立」は、職場の人間関係不良やいじめが、別の言葉として置き換わってしまっている印象もあります。
その意味では「職場環境調整義務」という既存の概念で整理した方が、現実的かつ理解しやすいのではないかと感じました。
産業医は「調停者」ではない
次に、産業医の立場から申し上げると、人間関係の「調停」にまで関わるべきではないと考えています。産業医は調停者ではなく、基本的には健康に関する専門家・助言者です。
ですので、職場の人間関係のもつれに、産業医が介入しすぎるのは適切ではないと思います。また、この事例のように、当事者の都合の良い「切り取り」や一方的な主張に基づいて判断するのは非常に危険で、産業医がどちらが正しいとか悪いといった「正義の判断」をすることは不可能です。そうした点も、常に注意が必要です。
職場文化を理解せずに「孤立」を一般化する危うさ
もう一つ大事なのは、こうした問題には職場の「文化」が大きく影響する点です。たとえば、自衛隊や消防隊などでは、命を守るために強い口調や指示が許容される一方、別の職場では許容されないなど、許容される言動の範囲は職場ごとに異なります。
この事例のようにスキルや芸が重視される職場では、内部に競争関係があることも自然で、ある種の「孤立」が生まれるのも当然の現象かもしれません。たとえるなら、部活でレギュラーになれなかった生徒が「孤立した」と感じることはあり得ますが、それに対して教師が不自然に介入すれば、逆に不公平になることもあります。
このように、健全な競争や切磋琢磨がある中での「孤立」は、必ずしも問題ではない場合もあるため、職場の文化や背景を無視して「孤立=悪」とすることは危ういなと思います。
一般化せず、文脈に応じた判断を
産業医として意見する場合も、企業文化や職場の文脈を十分に踏まえる必要があります。それを無視して「職場での孤立はよくない」と一般化してしまうと、「産業医は職場を分かっていない」と見なされかねません。
今回のような事例についても職場ごとの文脈を丁寧に読み解く姿勢が大事だと思います。
小島(弁護士)
判決から見える支援体制の機能と限界
今回の判決全文を読んでいて感じたのは、社員相談窓口や産業医、保健師などが非常に丁寧に対応していたように見えるということです。
たとえば、産業医との面談について「上司には言わないでほしい」と本人が希望し、実際にそれを守って面談が秘密裏に行われていたことなど、セーフティネットとしての機能がしっかり働いていた印象があります。
職場文化との“すれ違い”がもたらす違和感
ただ一方で、そうした対応が「一般的な産業保健」「一般的な相談窓口」として動いていた印象もあり、職場や事業そのものの文化・風土とのあいだに、どこかズレがあったようにも感じました。
つまり、形式的には正しく動いていても、その職場の価値観や空気感と噛み合っていなかったことで、結果的に本人との関係性を“依存的”なものにしてしまったり、むしろ本人の混乱を強めてしまったようにも見えます。
支援が「分断」を生むリスク
組織内での支援機能がそれぞれバラバラに動いてしまうと、本人の中でも混乱や誤解が生まれやすくなります。たとえば、どの相談窓口で話をしても「この会社はこういう組織なんだ」「私の立場はこういうものなんだ」と共通のメッセージが伝わらないと、それぞれの窓口で異なる物語が形成されてしまう。
こうした状態は、特に“複数の文脈で話をしてしまいがちな人”にとっては、かえってその傾向を強めてしまうリスクがあります。
組織内の機能は「統合」されるべき
最終的に、今回のケースでも、社内の支援機能があったにもかかわらず、当事者が本当に救われたとは言い難い結果になっています。
それは、おそらく各機能が個別には正しく動いていたものの、「組織全体としての統合的なメッセージ」がなかったからではないか。
つまり、リスクマネジメントや安全配慮のための仕組みがあっても、それが組織として統合されていなければ、むしろ分断を生んでしまうこともあるということです。
支援機能は「法人格としての統一性」を持てているか?
このあたり、熊井先生にもぜひ伺ってみたいのですが、たとえばハラスメントの事案が起きたとき、相談窓口、産業保健、人事といった複数の機能がどう連携しているか。いわば「社内の駆け込み寺」のような場所が複数あることが、一見すると良いことのように思われがちですが、それぞれがバラバラに対応してしまうと、かえって混乱や孤立を助長してしまう可能性もある。
だからこそ、それぞれの機能が「ひとつの法人格」の一部として、価値観や対応の方向性を共有できていることが、非常に重要なんじゃないか――そんなことを今回強く感じました。
井上(司会)
小島先生のお話を受けて、社労士としてのご経験から、社内ルールや実務対応について、熊井先生のご意見いただければと思います。
熊井(社労士)
職場での「孤立」とは何か──定義と介入の判断
まず「孤立とは何か」という定義の部分がとても重要だと感じています。改めて調べてみたのですが、職場での孤立というのは「一人だけ離れてつながりや助けがない状態」であり、それが業務に明らかな支障をきたしているのであれば、会社としては一定の介入が必要だろうと考えています。
ただし、孤立という言葉には多様な要素が含まれており、丁寧な整理が求められます。たとえば、「ランチに自分だけ誘われない」「逆に一人でいたいのに巻き込まれる」など、些細に見える人間関係の不一致も、孤立と捉えられることがあります。こうしたケースは私も調査の現場で日常的に耳にすることで、良し悪しの問題ではなく、捉え方や感じ方に大きな幅があるということを理解しておく必要があります。
社内ルールは「パワハラ指針」から組み立てるのが現実的
ルール作りに関しては、ゼロからオリジナルで作るのは非常に難しいため、「パワハラ防止指針(令和2年厚生労働省告示第5号)」に基づいて組み立てるのが実務的だと思います。
指針には「必要のない隔離」「仲間外し」「無視」といった、人間関係からの不当な切り離しについて明確に触れられており、「職場で孤立させることは望ましくない」という趣旨も本文に明記されています。
初動対応のポイント──丁寧なヒアリングと希望の確認
相談があった際の初動対応としては、まず事実・結果・感情を分けて丁寧にヒアリングすることが大切です。
そのうえで、実現可能かは別として、ご本人の「どう解決したいのか」という希望を確認することが、会社側が忘れがちなポイントだと思います。また、問題を整理する際には、「法令違反の疑い」「業務遂行上の支障」「文化・価値観に関わる問題」などを切り分けて考えることが必要です。
人間関係調整の範囲と企業の裁量
どこまで調整すべきかについては、法律や就業規則に抵触するような問題があれば、会社には一定の対応責任があります。たとえば、ハラスメントが明確に確認された場合には、加害行為者の配置転換なども検討されるべきです。
一方で、「職場を家族的にやりたい」といった企業文化やポリシーもまた、経営の裁量の範囲です。ただし、そのポリシーが現代の価値観や法令に適合しているかどうかは、定期的に見直す必要があります。
ハラスメント対策との連携と明確な運用ルール
ハラスメント対策との連携についても、特別な新制度を設けるというよりは、措置義務の基本に立ち返ることが重要です。
「方針の明示」「相談体制の整備」「迅速な対応」「プライバシー保護」といった原則が指針に明記されており、これに従ってルールを作れば、実効性のある制度になります。
相談対応には「取り扱いの範囲」の線引きが必要
現場で日々感じているのは、会社として「取り扱う範囲」を明確にしておかないと、相談が無限に広がってしまうということです。
たとえば、地域のトラブル、PTAのグループLINE問題、不倫や恋愛のもつれといった私的な事柄まで相談に含まれることもあります。そういったときに、「会社としてここまでは扱いますが、ここから先は対象外です」と線を引けば、属人的な対応を防ぐことができます。
支援対象者の性質を見極め、過度な関与を避ける
最後に、支援対象者の中には、精神的に非常に不安定な方や、被害妄想的な訴えを複数の窓口に同時に発信してしまうような方もいらっしゃいます。「人事にも、保健室にも、産業医にも、上司にも、ユニオンにも訴えた」というケースもあり、対応する側がそれぞれ異なる反応をすると、本人の混乱をさらに助長することになりかねません。
そういった方に対しては、倫理的な説得や共感だけではなく、「ここまでが対応範囲です」と冷静に伝え、健康面からのサポートへ移していくことも必要です。
五十嵐(産業医)
孤立しやすい属性の方へのセーフティーネットは予防法務・産業保健の両面で重要
社内で孤立しやすい属性の方に対して、セーフティーネットをどう機能させるかという点は、予防法務としても、産業保健としても非常に重要なテーマだと思います。
「ガイドライン通りに粛々と」が基本スタンス
先ほど熊井先生がお話しされたように、「粛々とガイドラインに基づいた対応を行うこと」が基本であり、それがもっとも信頼されるやり方だと私も思います。
そのうえで、窓口の設置や、できること・できないことを整理して共有する場を設けることが必要です。
本人の声を受け止める「場」としての機能が重要
相談窓口や医療職が担うべき役割は、問題の調整役ではなく、「本人の話をきちんと聞く場」「感情のクッションとなる場」として機能することだと思います。これは予防法務の一環としても重要な機能だと感じています。
必要に応じて「場」を設定し、納得感を得るプロセスを
現実には、産業保健職や相談窓口だけで完結できないケースも少なくありません。そうした場合には、職場や上司にも情報共有をはかり、「関係者が集まり意見を出し合える場」を設けることが必要です。そして、会社側が何ができて・何ができないかを本人に明確に説明し、納得感を得てもらうことが、対応の基本になると思います。
対応の基本は「属性によらず一貫性を保つこと」
「パフォーマンスの問題がある」「職場で浮いてしまう」などのケースに限らずLGBTQの方、海外単身赴任の方など、孤立しやすい状況はさまざまに存在します。
そうしたマイノリティに対して特別扱いをするよりも、基本的なスタンスや対応の枠組みは共通でよいはずです。
粛々と、指針に沿ったプロセスを尽くす
指針に基づいた対応を粛々と行い、そのプロセスをきちんと尽くすこと――これが会社としての責任であり、信頼につながる対応なのだと考えています。誰に対しても、一貫した方針で、丁寧に対応していくことが、結果的に組織の健全性を支えることになると思います。
小島(弁護士)
実は「やること」は変わらない──その重要性
そうですね。結局のところ、やるべきこと自体はそんなに特別な対応が必要なわけではなく、基本的には「いつも通り」「決められたことを丁寧にやる」ということに尽きると思います。
ただし、それを忘れずに実行するためには、「こういう方」のことを理解しているという経験や視点が欠かせません。
想像力がなければ「いつも通り」が崩れる
実際には、「いつもの通り」ができなくなってしまうケースが多くあります。たとえ制度があっても、実務上はうまく機能しない。それを防ぐためには、相手がどんな状態にあるのかを理解しようとする姿勢、つまり想像力や思考を止めないことが必要なんだと思います。
私はあえて「妄想力」と言っていますが、それは決して相手にそのままぶつけるということではなく、「この人の中で何が起きているのか」を想像し、想定の範囲内におさめて対応するという意味です。
「想像しながら、やるべきことをやる」ことの難しさ
つまり、難しいのは、相手の中で起きていることを想像しながらも、「やるべきことをやる」「役割を明確にした上で動く」ことです。制度的にはルール通り、プロセス通りにやるのが正しい。
でも、相手の状態や言動に巻き込まれると、それがうまくできなくなってしまう。現場では、まさにそこが一番のハードルなんだと思います。
経験と専門性が支える「ぶれない対応」
だからこそ、こういったケースに慣れている専門家や経験者が関わることの意味は非常に大きいと思います。
相手がどんな反応をするか、どこで混乱が生じやすいか、どう対応すればいいか――そうした引き出しを持っている人がいることで、組織として「いつものやるべきこと」をぶれずに実行できるようになる。あらためて、経験と専門性の重要性を感じました。
五十嵐(産業医)
「粛々とやる」中で現場が取る柔軟な工夫
実際の現場対応では、「粛々とやる」と言いつつも、トラブルになりそうなケースでは対応を手厚くすることがよくあります。たとえば、対話の回数を増やしたり、感情面にも配慮したりすることです。それでも、あくまで基本の枠組みやプロセスの中で対応するということが前提にあります。
小さなすれ違いによる感情のもつれによって訴訟に発展したのでは
この事例でも、おそらくどこかで感情的なもつれが生じる瞬間があったのではないかと感じています。 「訴えても誰も動いてくれない」「相談したのに何も変わらなかった」――そうした体験が積み重なって、訴訟にまで至ってしまったのではないでしょうか。関係者間がやるべきことをやっていたとしても、本人の感情と組織側の対応のあいだに、どこかでズレや齟齬が生まれてしまったのではないか。小さなすれ違いが重なり、結果として構造を複雑化させてしまったように感じます。
熊井(社労士)
妄想や期待の揺れをどう扱うか
企業に依頼されて実際に面談をする方の中で、病名はともかくとして、妄想的な訴えや、非常に期待値が高く、それが後にガクッと下がってしまうような「揺れ」のある方がいらっしゃいます。
こうした方にボリュームとして「手厚くする」ことで、かえって状況がややこしくなることもあると私は思っています。
ルールを決め、先手を打つ「半歩前」の関わり
私が実務の中で意識しているのは、「先駆ける」という姿勢です。つまり、半歩だけ前に出て、対応の主導権を確保する。そのうえで「できないことはできない」と明確に伝える。
たとえば、「面談時間は50分で全員同じです」といったように、あらかじめ枠を決めておく。そうしないと、対応する側――特に担当者や相談員が疲弊してしまうこともありますが、結果として訴えのある人を守ることにもなると思っています。
この「半歩前の関わり」が、のちの混乱や過剰な期待を防ぐ意味での「手厚さ」になるのだと、私は捉えています。
「振り幅」が大きい方への対応と落差への備え
いわゆる「振り幅が大きい」方というのは、一度上がると、その分大きく下がることがあります。病名で説明するかどうかはともかく、現場ではその現象をよく目にします。
その意味でも、私はいつも人事や相談担当の方に、「最初に期待値を上げすぎると、必ず反動が来ますよ」とお伝えしています。
対処の基本は「キャップ(限界値)を決めておくこと」
毎日実務を担当している立場として、私が大事だと思っているのは、「どこまで対応するか」という限界値――キャップをきちんと決めておくことです。
対応の幅を無制限にしてしまうと、かえって混乱やリスクを招くことになる。現場での「対処」という観点では非常に重要だと思っています。
五十嵐(産業医)
先手を打つ「説明の丁寧さ」が本当の意味での手厚さ
たとえば「丁寧に説明する時間を少し増やす」とか、「後出しにならないように、あらかじめ本人の理解が深まるまで説明しておく」といった工夫――これこそが、本当の意味での「手厚くする」ことなのだということですね。
井上(司会)
今回の裁判例からの教訓を含めて、小島先生に議論を総括していただけますでしょうか。
小島(弁護士)
北風と太陽の両面を「一つの人格」で担う意義
よく「北風と太陽」のたとえで、厳しさと寄り添いを別の担当者が担うべきだという考え方がありますよね。たとえば、人事は厳しく、産業保健は優しく、といった役割分担です。
でも私は、あまりに分けすぎることで、かえってご本人が「同じ会社の中に全く違う人格がある」と感じてしまう危険があると思っています。そうなると、ご本人の中でも「会社と向き合う自分」を統合的に捉えられなくなってしまう。
支援が「分裂感」を生まないように
複数の担当者がバラバラに関わると、「この人は温かく話を聞いてくれたけど、あの人は冷たかった」といったように、支援の一貫性が損なわれる。その結果、支援される側は「もっと寄り添ってくれるはず」「厳しいのは不当だ」と感じてしまうことがある。
だからこそ私は、できる限り一つの人格の中で北風と太陽の両面を示すことが大事だと思っています。
法人の機能としての限界と冷静な線引き
産業保健や相談室の役割は、精神科医やカウンセラーのように全面的に寄り添うものではありません。あくまで「法人の中の一機能」です。
したがって、支援の中にも法人としての限界や厳しさ――いわば「北風」も存在していることを明確に伝えるべきです。
支援対象者の特性によって対応を見直す必要性
こうしたケースで難しいのは、「いつもの対応」がうまくいかないことがある点です。普段であれば「問題と向き合う力」がある人が、過労などのきっかけで一時的にそれを失ってしまっているような場合とは異なるわけです。
「いつも通りやる」だけでは不十分で、むしろ支援側の姿勢や枠組みそのものを研ぎ澄まし、原点に立ち返る必要があると感じています。
ハラスメントの「感じ方」と「制度上の扱い」は別物
法律家として言えば、ハラスメントに該当すると判断できる事案はごく一部です。多くの場合、被害を訴える本人が「ハラスメントだ」と主張していても、事実としてそれが認められるかどうかは別の話になります。
ただ、本人の主観の中で困難や苦しさを抱えていることは事実であって、それを「感じるハラスメント」として職場改善につなげていく視点は必要です。
二項対立ではなく「独自の領域」として扱う必要性
「これはハラスメントか、そうでないか」と二者択一で処理しようとすると、現場は混乱します。「感じるハラスメント」は、法的に処断すべきハラスメントとは別の次元として、独立した領域として捉えるべきです。
「ハラスメントではないから何もしません」ではなく、感じる苦しさや背景を受け止めつつ、処罰や会社責任に直結させない――そうしたバランス感覚のある支援が必要です。
教育とマネジメントの中で支援を位置づける
だからこそ、企業側はリスク回避のためにも、感じるハラスメントへの対応をマネジメント教育や職場の対話に落とし込む必要があります。
今回のケースも、「ハラスメントだから争いになった」というより、感じ方の問題が適切に扱われなかったことが背景にあるのではないか。そうした教訓を、実務にどう生かしていくかが問われていると感じます。
井上(司会)
最後に、五十嵐先生、熊井先生から一言ずつお願いします。
五十嵐(産業医)
都合のいい情報だけを切り取って相談するリスク
自分に都合の良い部分だけを切り取って相談すると、相手は「そうだよね」「あなたは悪くないよね」と言ってくれる。しかし、それが繰り返されると、自分には非がないという感覚がどんどん強まっていく。
特に他責傾向がある場合、それが強化されてエスカレートしてしまう――そういう構図も現実にあるのではないかと感じました。
孤立がさらなる孤立を生む構造
最初はただの孤立だったとしても、周囲からの共感や擁護の言葉が、「自分は正しい、悪いのは会社だ」という考えを助長してしまい、結果的にさらに関係が断絶していく。つまり、孤立が孤立を呼ぶ構造ができてしまう。そうした流れも意識する必要があると思います。
産業医が「全肯定」に陥らないことの重要性
産業医としては、もちろん当事者の話に耳を傾けることは大切ですが、その人の言い分を過度に肯定したり、感情に寄り添いすぎないことも、同じくらい重要だと感じています。その気持ちに寄り添いすぎることで、かえって本人の孤立感や対立構造を深めてしまう危険があるからです。
セーフティネット=全肯定ではない
「セーフティネット」としての役割は、すべてを肯定することではない。孤立した人の背景には複雑な事情があり、同時に職場側にもまた事情があります。
だからこそ、産業医はそのどちらにも偏らず、冷静な立場で支援する必要がある。この事例から学べる産業医へのメッセージとして、僕自身が強く感じたのはその点です。
熊井(社労士)
ハラスメントかどうかより、「問題」と「希望」に焦点を
ハラスメントかどうかというのは、最終的には評価の問題です。たとえば労災認定のように、法的判断が求められる場面ではきちんと結論を出す必要があります。ただ、職場で対応する際には、私はいつも「今の問題は何ですか?」「どう解決したいと考えていますか?」という2点に焦点を当てて話を聞くようにしています。
「これハラスメントなんですよね?」という問いかけが相談の入り口になることもありますが、最終的にはこの2点を確認し、その問題が会社で扱うべき労務の問題なのか、それとも健康の問題なのか、丁寧に整理していくことが大切だと考えています。
多方面に相談する人への対応──情報の集約とルールの明示
同時に複数の窓口に相談してしまう方というのは珍しくありません。私自身もそうした方に時々お会いします。そのような場合、私が実務で行っている対応のひとつが、会社内のコアとなる相談対応機関に相談を集約してもらうという方法です。
そこでは、「相談内容についての秘密を守る義務は、あなたにもあります」とお伝えしています。たとえば、「この相談機関でこんなことを言われた」と周囲に言いふらすことは、相談者自身のルール違反になる、ということを明確に伝えます。この点については、口頭だけでなく文書でも伝え、同意のサインや返信をもらうようにしています。
情報操作やルール違反には冷静かつ厳正に対応
一度預かった相談内容について、相談前後に勝手に情報操作したり、秘密を破ったりすることは認められません。もちろん、相談者の抱えている問題については誠実に受け止めますが、「ルールを守ること」は当然相談者にも求められることです。
繰り返しになりますが、こうしたルールが守られない状態が続けば、職場の秩序は維持できなくなります。そのためにも、「あなたは職場で働いている一人であり、服務義務を負っている」と伝えることで、相談者本人の混乱も減らすことにつながると思っています。
今回、違う観点を持つ専門家の皆さんのお話を伺って、私自身もさまざまな気づきがあり、事柄の整理ができる時間となりました。