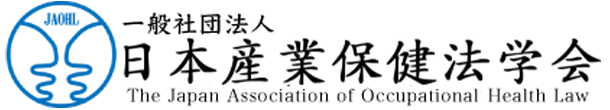「『リスク創設者管理責任論』の産業保健の領域への応用」を読んで(広報 on HP)
- 「産業保健法務主任者の声」ページ開設のお知らせ
- 「広報 on HP 第33号」公開のお知らせ
- 「広報 on HP 第32号」公開のお知らせ
- 【申込受付中】11月15日(土)開催 オンライン事例検討研修
- 「広報 on HP 第31号」公開のお知らせ
- Society of Occupational Medicine(英国産業衛生学会)との連携協定を結びました
- 「広報 on HP 第30号」公開のお知らせ
- 学会事務局・夏季休業期間について
- 英文誌(JOWHSR)Vol.4-1発刊のお知らせ
- 産業保健法学会誌第4巻第1号発刊のお知らせ
岡田 俊宏(日本労働弁護団常任幹事 弁護士)
労働者側で労働相談を受ける中で感じることは、個人事業者等として扱われている人の中には、かなり従属的な働き方をしており、本来、「労働者」として保護されるべき人が相当数含まれているということである。裁判所で用いられている「労働者」性の判断基準は、現代の働き方にはフィットしておらず、見直しが必要であると考えているが、仮に今の裁判所の考え方を前提にするとしても、法的には「労働者」と判断されうる個人事業者等が多数存在する。まさに、三柴先生が指摘されるような「労働法の適用逃れ」「雇用責任逃れ」の実態があるといえる。
使用者に雇用責任逃れをさせないためにも、労働者性の推定規定を設けること(すなわち、使用者が、労働者でないことを証明しない限り、労働者として扱うこと)などが必要であると考えている。また、伝統的な「労働者」概念は、工場労働等が念頭に置かれており、現代の働き方には適合していない。例えば、労働者性の判断基準の1つとして時間的場所的拘束性があるが、時間や場所の裁量がある労働者はいくらでも存在するのであり、「労働者」概念やその判断基準自体を見直していくことも必要であろう。なお、プラットフォームワーカーの中にも、労働基準法上の労働者性が認められる者は存在すると考えている。このような人たちは、「労働者」として、保護の対象とすべきことはいうまでもない。
その上で、「労働者」には当たらない個人事業者等の安全衛生を考えることも、極めて重要なことである。安全衛生は、働く人の生命と健康の問題であるから、「労働者」か個人事業者かによって保護に差を設けるべきではない。従前の労働安全衛生法も、直接の労働契約関係を中心としつつ、それを超えた関係者への規制も行ってきたが、その方向性をさらに押し進めるべきである。
個人事業者等の中には、もちろん、注文者と対等に交渉し、自律的な働き方をしている人も存在するが、その多くは、弱い立場に置かれているといえる。例えば、注文者からの無理な要求を断れなかったり、安全衛生に必要な費用を代金に計上することができなかったりすることは、よくあることである。ルールを考える際には、そのことを念頭におく必要がある。
労働安全衛生法は、もともと、業種ごとに、後追いで規制を作ってきた面がある。しかし、本来、事故が起こってからでは遅いのであり、あらかじめリスクを想定して積極的に規制をすることが望ましいと考える。また、働き方は絶えず変化しており、今後もITやAIの進展や産業構造の変化等により、新しい産業や働き方が次々に生まれることが予想される。したがって、それに対応できるような普遍的なルールをあらかじめ考えておく必要がある。その際に、三柴先生が提唱されている「リスク創設者管理責任論」という考え方は、極めて魅力的な考え方と思われる。業種毎にリスクは様々ありうるが、リスクの創設者が責任を負うという共通の基本的な考え方に基づき、法改正を行っていくべきである。
プラットフォーム事業者も、完全な仲介者であることは少なく、一定のリスクを創設していることが多いので、仮に「使用者」と認められない場合にも、リスク創設者という観点から、それに応じた責任を負わせる方向で考えるべきであろう。なお、アルゴリズム管理によりプラットフォームワーカーがプレッシャーを強く受けているとの点は、先生方が指摘されているとおりだと思う。ワーカーの皆さんから話を聞いてみても、実際にそのような印象を持っている人が多い。プラットフォームワーカーの安全衛生を考える際には、その点を踏まえる必要がある。
規制の実効性については、私も、小島先生と同様に、罰則無しで果たして実効性があるのかという疑問をもっている。soft lawにもメリットはあるし、罰則を設けることのデメリットも理解できるものの、実効性を高め、公正競争を確保するためにも、規制の内容によっては、罰則を設けることも積極的に検討すべきである。また、三柴先生の指摘されるとおり、安全衛生を担当する労働基準監督官の育成も重要な課題であろう。弁護士として労働基準監督官と話す機会もあるが、担当者の能力や意欲等によって、対応が大きく変わる印象がある。また、監督官の数が業務量と比べて少なく、調査等に十分に時間をかけることが困難になっているのではないかと感じることも多い。この分野に十分な予算を充て、人員を確保しつつ、専門性や現場感覚を習得させていくような方策が必要と思われる。
最後に議論されている産業医の質の問題についても、同感である。労働者側弁護士からみると、十分な専門性を備えておらず、使用者の言いなりになってしまっているような産業医も時折みかける。産業医の専門性や独立性を高める方策についても、引き続き検討する必要があるだろう。